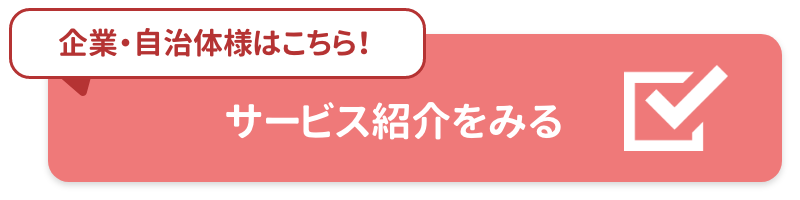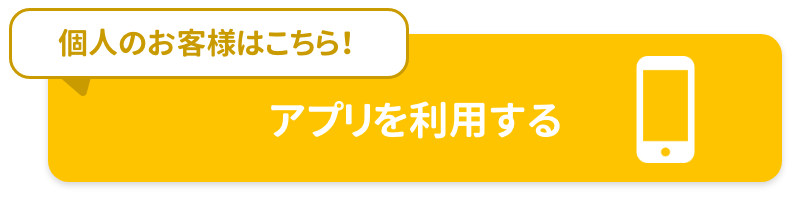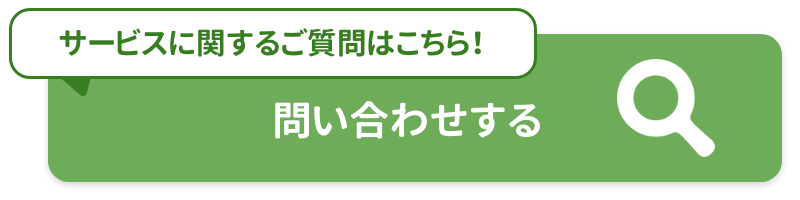法人向け
特定保健指導第4期はいつから?アウトカム評価など変更点のポイント
生活習慣病を予防するために実施される特定健診・特定保健指導。第3期の内容が見直され、特定保健指導第4期が2024年から開始されます。第4期の大きな変更点として「アウトカム評価」があげられます。アウトカムとは結果を意味し、第4期では身体の変化を具体的な数値目標として設定しており、成果を重視した指導が可能になりました。しかし、詳しい内容を理解できていない方も多いでしょう。
本記事では、特定保健指導第4期の変更点を詳しく解説します。また、従業員が特定保健指導の対象者にならないための対策も紹介します。
目次
そもそも特定保健指導とは?

「特定保健指導」とは、医療保険に加入している40歳から74歳の方のために行われる保健指導のことです。特定健診(※)で特定の基準以上に達した人、つまり、生活習慣病を発症する可能性がある方に向け、保健師や管理栄養士などの専門スタッフが生活習慣を改善するサポートをします。
特定保健指導では対象者に対して面談を実施し、個々に合ったアドバイスや行動計画を作成します。また、メールや電話などでも支援を行い、生活習慣の改善を目指します。
※特定健診:40歳から74歳の方が対象のメタボリックシンドロームに着目した健康診断
特定保健指導第4期はいつから?

特定保健指導は平成20年度(2008年)から始まりました。定期的な見直しを経て、第4期は令和6年(2024年)に開始されます。
特定保健指導第4期の変更点・ポイントは?
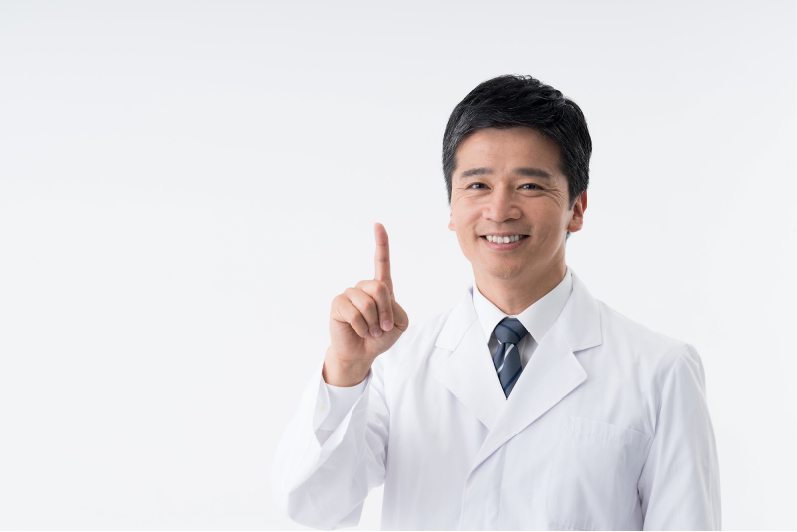
特定保健指導第4期の変更点・ポイントには、以下の5つがあげられます。
- ICTの活用
- アウトカム評価の実施
- 達成状況の見える化
- 健診項目の見直し
- 飲酒と喫煙に関する質問内容が変更された
ここでは、それぞれの詳細を解説します。
ICTの活用
ICT(Information & Communications Technology)とは「情報通信技術」のことであり、通信技術を活用したコミュニケーションを指します。在宅勤務・遠隔地勤務などの多様なニーズに対応・地域格差をなくすため、特定保健指導にも積極的にICTを活用することが方針として盛り込まれました。
ICTにより遠隔で行う保健指導に関しても、評価水準や時間設定などは対面と同等であるとしています。
アウトカム評価の実施
特定保健指導第4期の大きな変更点にあげられるのが「アウトカム評価」の導入です。今までの特定保健指導は面談や電話など、結果ではなく支援内容にそれぞれポイントが加算される仕組みでした(5分の電話で10ポイントなど)。
第4期ではアウトカム評価の主要達成目標として「腹囲2cm、体重2kg減」を設定し、達成すれば180ポイントを付与することとしています。身体の変化を具体的に数値で評価できるため、しっかりと結果が出たかを重視できます。
達成状況の見える化
第4期では主要達成目標である「腹囲2cm、体重2kg減」だけでなく、その過程である「腹囲1cm・体重1kg減」も評価に値するため、達成状況が見える化できます。
他にあげられている評価の対象は以下の5つです。
- 食習慣の改善
- 運動習慣の改善
- 喫煙習慣の改善
- 休養習慣の改善
- その他の生活習慣病の改善
上記5つ、「腹囲1cm・体重1kg減」の達成、面談や電話などの活動内容にはそれぞれポイントが設定されています。「腹囲2cm、体重2kg減」が達成できない場合でも、その他の項目のポイントを合計して180ポイント以上になれば、特定保健指導を終了できるとしています。
健診項目の見直し
第4期では健診項目の見直しもされています。見直しにより変更されたのは中性脂肪の項目です。第3期までは中性脂肪の判定基準が「空腹時採血150mg/dl以上」と設定されていましたが、そこに「随時採血175mg/dl以上」が追加されました。
空腹時:食後10時間以上
随時:食後3.5時間以上10時間未満
飲酒と喫煙に関する質問内容が変更された
第4期では飲酒と喫煙に関する質問が細分化され、詳細な対象者選定を可能にしています。喫煙の質問「現在、たばこを習慣的に吸っていますか」の回答は「はい」しかありませんでしたが、第4期では習慣的に喫煙している者の定義を明確にし、回答選択肢を3つに細分化しています。
飲酒の頻度に関する質問「お酒を飲む頻度はどのくらいですか」に対する回答は「毎日」しかありませんでした。第4期では、月に1日未満、週3~4日など回答選択肢が8つに増えており、健康上飲めない場合と区別できるよう質問内容が設定されています。また、1日あたりの飲酒量の回答選択肢も3つから5つに増えました。
従業員が特定保健指導対象になるのを防ぐには?
従業員が特定保健指導対象になるのを防ぐには、以下のような対策があげられます。
- ヘルスケアアプリの導入
- 生活習慣を改善するための研修などの実施
- 運動習慣を身につけるイベント・部活などの導入
それぞれの詳細を解説します。
ヘルスケアアプリの導入
ヘルスケアアプリを導入すれば、従業員が気軽に生活習慣改善の方法を相談できるようになります。従業員自身が普段から生活習慣改善の相談ができるため、自分で改善に必要な行動を取りやすくなります。
いつでも利用できるサービスを導入すれば疑問が生じた時に相談できるので、改善のために行動がしやすくなるでしょう。
生活習慣を改善するための研修などの実施
どのような生活習慣をとっていると生活習慣病になりやすいのか、また、その生活習慣をどのように改善すれば生活習慣病になるリスクを減らせるのかなどを指導する研修やセミナーを実施するのもおすすめです。
従業員自身が正しい知識を身につけることができれば、自ら生活習慣を改善していけるようになります。
運動習慣を身につけるイベント・部活などの導入
従業員に対して運動習慣を身につけさせるようなイベントの開催、運動部などの導入、ジムを用意するのも一つの方法です。企業が従業員に運動習慣を身につけられるような施策を取り入れれば、生活習慣病になるリスクを減らせるでしょう。通勤の際に自転車通勤を促すのもおすすめです。
特定保健指導の対象になる従業員を減らす対策として「HELPO」
従業員が特定保健指導対象になるのを防ぎたいと考えている経営者や人事労務担当者の方におすすめなのが、ヘルスケアアプリ「HELPO(ヘルポ)」です。HELPOは24時間365日、いつでも医療専門チームに相談できるスマホアプリです。医療専門チームには医師や看護師、薬剤師などが在籍しているため、幅広い相談内容に対応できます。
「食事のアドバイス」「運動後の体のケア」のように健康維持に関する内容や、心や身体の悩みについても気軽に相談できます。
HELPOには歩数機能があるため歩数や消費カロリーを確認でき、運動への意識を高めることが可能です。気になる方はぜひ、導入を検討してみてください。
特定保健指導第4期に備えて従業員の健康をサポートしよう
特定保健指導第4期では、「腹囲2cm、体重2kg減」といった「アウトカム評価」を導入し、具体的な成果が評価されるようになります。また、健診項目や質問内容の追加、ICTの活用などさまざまな面で変更・改善されました。第4期は2024年から開始されるため、内容をしっかり理解しておく必要があります。同時に、従業員の健康をサポートする対策も行いましょう。
従業員が特定保健指導の対象者にならないための施策としておすすめなのが、ヘルスケアアプリ「HELPO」です。HELPOは生活習慣や身体の悩みなど、さまざまな内容に対して医療専門チームがアドバイスしてくれます。気になる方はぜひ、導入を検討してみてください。